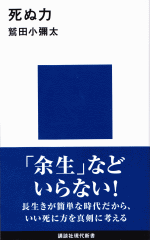
「余生」などいらない!
長生きが簡単な時代だから、いい死に方を真剣に考える
『死ぬ力』 クリスティのミステリにになぞらえて
『死ぬ力』というテーマで講談社現代新書に書かないか、という注文を受けた。「死」に関する本は、何冊か書き下ろしている。それに「哲学」で「死」は身近なテーマだ。避けて通れない。しかもわたしにとって、死はどんどん間近になっている。「遺書」に近いものになっても困るが、書く力がふつふつと湧いてきた。これも「死ぬ力」にちがいない。予定の仕事を後回しにしても書きたい、と決した。だが難しい問題がある。
二〇世紀、もっとも「死」の想念(哲学)で影響を与えたのは、ハイデガー『存在と時間』(1927)である。わたしにとっては、木田元さんの「解釈」(『ハイデガー『存在と時間』の構築』2000)である。しかし、ハイデガーでは、どんなに平明にいっても、「死」と向き合うとき生まれる先きのばし不能な「生きる」覚悟にこそ、人間本来の生き方がある、というのだから、人の心に届きにくい。屁理屈に思える。
死に臨んで、はじめて真の生き方を知ることができる、というのはたしかに「比喩」としてはわかる。でも、それでは、遅きに失する。「死ぬ覚悟」と、「臨死の覚悟」とは異なる。酔うと、「死ぬ覚悟なのだ!」と絶叫し、階段落ちをする若手の「哲学」研究者がいた。手に負えなかった。
わたしが採ったのは、アガサ・クリスティの作品名(と内容の一部)をなぞって、「死」がもつ巨大で、卑近(familiar)な力を論じようとする、行き方である。クリスティは、第二次大戦でイギリスがナチスドイツ軍の猛攻を受けるなか、「遺書」のつもりで、彼女の死後出版してほしいといって、ポアロもの『カーテン』とミス・マープルもの『スリーピング・マーダー』を書いた。二作品は、四〇年余後に日の目を見るが、彼女自身の「死」に臨んだもの、さらには人間の死一般にかんするする鋭いセンスに満たされたもの、として読む(解釈)することができる。それに、引退を決めたポアロが最後にと思って引き受けた事件を集めた『ヘラクレスの難業』(ヘラクレス=エルキュール)他、ミステリには「死」が満載なのだ。
ポアロは『カーテン』で「自死」する。そのポアロは、じつはシャーロック・ホームズと同時代人(あるいはポアロのほうが年上という説もある)である。超高齢で、自分の生をどのように閉じることができるのか、それが『カーテン』の主題だ。「閉幕の思想」である。ハイデガーにない問題意識だ。ポアロの「死ぬ力」が試される。ま、「深読み」かも知れないが、「自殺」も「殺人」である、という意味もここで語りたかった。さらにいえば、「なぜ人を殺してはいけないのか?」に続く問題だ。
それにしても、「死」というと、なんだかしかめっ面になる。愉快とはいわないが、快活に論じたい。そう思ってきた。ミステリの多くは、「死」に過剰な思い入れをする。クリスティも例外ではない。たしかに、今日、家族が縮小し、「死」はまれにしか出会わなくなった。「死」を過剰に見がちになる。しかし、死は、戦時も平時も、古今東西、無数にある。問題は、個々の死とともに、人間に共通な死(の力)を見極めることだ。そこにどれだけ接近できたか…。
(PR誌『本』講談社 16/3 抜粋)




